小説版イバライガー/第14話:サウンド・オブ・サンダー(前半)
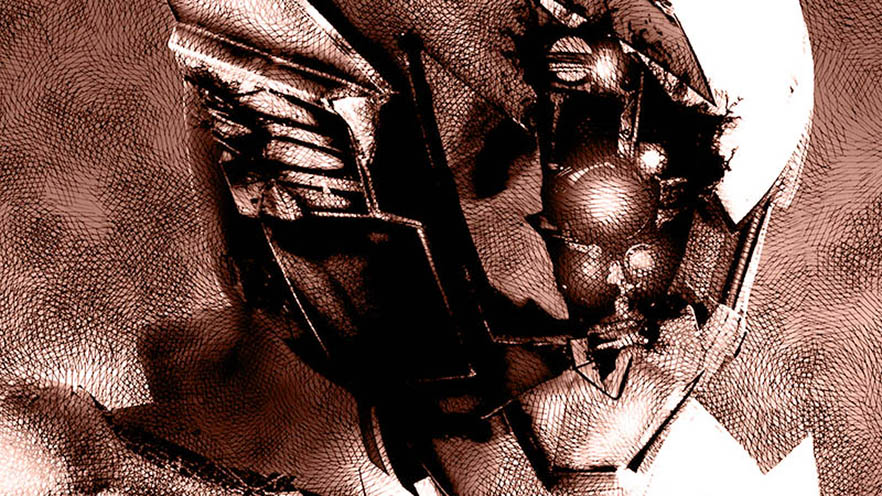
OP(アバンオープニング)
主婦や女子高生が、笑いながら通り過ぎていく。
あの連中は、タクシーには乗らない。
ビジネスマンも乗らない。この辺りでは、誰もが車に乗っている。
タクシーを使うのは出張や観光で訪れた者くらいだが、平日の午後には、そういう人は少ない。
JR土浦駅ロータリーには、自分の他にも数台のタクシーが客待ちしているが、この数十分で客が乗ったのは3台だけだった。
以前は、つくばに向かう研究所の関係者がよく乗り降りしていたが、つくばエクスプレスが開通してからは、それもめっきり減ってしまった。
余計なモンを作りやがって。
思わず毒づいたとき、女が近付いてきた。
信じられないような美女だ。思わず見とれた。
我に返ったときには、女は後部座席に座っていた。
いつ、ドアを開けた?
車内が急に寒くなった気がする。
車が、動き出した。
俺は運転しているのか。行き先は訊いたか?
知っている。俺は行き先を知っている。
なぜ知っている? いつのまにか会話していたのか? 女はどんな声だった? 思い出せない。
話しかけようか。だが、口が動かない。いや、全身の感覚があいまいだ。寒い。寒くて凍えそうだ。
それでも身体は運転し続けている。抗えない何かが、自分を動かしているように感じる。現実感がない。
そうした感覚が、高架道を降りて土浦学園線に差し掛かった辺りで、すうっと消えた。
突然戻ってきたハンドルの感触に焦って、一瞬、タクシーは蛇行した。
後席に乗っている女はそのままだった。一声も発しない。
だが、何かが違う。
相変わらず美女だが、さっきまでの怖気は感じない。同じ女が、そっくりな別人に入れ替わったような。
バカな。こんな真っ昼間からタクシー幽霊かよ?
気にするな。すごい美女ってだけで、普通の客のはずだ。
目的地まで連れていけば、そこで終わり。後は、タクシー仲間や家族にすごい女を乗せたと自慢するだけ。
酒を飲むときのネタが1つ増えたというだけのことだ。
つくばのセンタービル前で、車を停めた。
女が、ぎこちない動きで降りていく。まるで操り人形のような動き。
ゆっくりと、振り返る。
その顔を見る前に、運転手はアクセルを踏んだ。
半開きのままのドアが、路上駐車の軽自動車にぶつかったが、構ってはいられない。
乗車料金も受け取っていない。それも知ったことではない。
早く、ここから離れなくては。
アレは見ちゃいけない顔だ。
何だかわからないが、近付いてはいけないものだ。
Aパート
シンは、周囲を見回した。
ミーティング・ルームに全員が集まっている。
いないのは、数日前に姿を消したミニブラックだけだ。
ちょいと里帰りと言っていたらしいから、ブラックの元へ行ったのだろう。
イバライガーブラックが何を考えているか不安ではあったが、止めるわけにはいかなかった。
自由にさせる。束縛しない。それが最初からの約束なのだ。それを破れば、生まれつつあるミニブラックとの信頼は崩れてしまう。
戻ってくるはずだ。ねぎもいる。ミニライガーたちが眠りについて、退屈だっただけかもしれない。
「始めるわよ」
エドサキ博士の声に、シンは我に返った。
博士がモニタを指差して話し始めた。「いい? 今回の作戦は……」
全員がモニタ前に集まり、一斉に覗き込む。
むぎゅ~~っと、おしくらまんじゅう状態になった。
ここはあくまでも一時的な隠れ家。
緊急に用意した場所だから、設備もありあわせのものだけだ。
離れて座って全員で見れる大型モニタなんてモノはないのだ。
「キツイ~~~~ッ!!」
「押すな~~~!!」
「つぶれるぅううう~~!!」
「いい加減にせんか、バカモノども!!」
博士が一喝して、ようやく離れた。
「もうモニタは見んでいいっ! ガール、このプリントを配ってちょうだい」
「プリントあるなら早く言ってよ~~」
マーゴンがボヤいた。いつもならシンも乗っかる。
が、今はそんな気分になれなかった。
プリントを見つめる。
初代イバライガー・サルベージ計画。
時空の狭間に消失した初代が、今も生きているのかどうかはわからない。
だが、シンもワカナも、初代の生存を信じていた。
時空の特異点は、過去でも未来でもない。いや、時間や空間といった概念自体が当てはまらない。
永遠であり一瞬でもある「点」そのものなのだ。
だとしたら『あの瞬間』が、あのときのまま、封じられている可能性がある。
初代イバライガーは、今も希望と悲しみの狭間にいるのかもしれないのだ。
その領域にもう一度アクセスし、連れ戻すのが『初代イバライガー・サルベージ計画』だった。
それを実現するために、ミニライガーたちは自らの身体を犠牲にしてまで、許容量を遥かに上回るエネルギーを蓄え続けているのだ。
エドサキ博士がプリントのページをめくりながら話し始めた。
「とにかく今回の作戦要旨をもう一度説明しておくから、全員しっかり頭に叩き込むのよ。まずミニライガーたちのカプセル設置。これはシン、ワカナ、イモライガーに担当してもらうわ。それぞれ1つずつの設置。いいわね?」
ワカナと、イモライガー=マーゴンがうなずいた。
シンは黙って腕を組んでいる。
「設置場所は、例の廃虚ショッピングモール駐車場。『あの瞬間』と同じエネルギー領域に到達できればいいだけだから、場所まで同じでなくてもいいのだけど、何が起こるか分からないことだからね。もしものときに周辺に被害を及ぼさないためにも、無人のショッピングモールを作戦エリアとする。厳密な場所はプリントのP4に記載してあるから」
みんながページをめくる。なんか、修学旅行のしおりを見ているような気分だ……と思ったら、P2に「バナナはおやつに入らない」などと書かれている。
くっ、こちらの思考を読まれている。さすがはエドサキ博士、あなどれない。
「Rとガールはモール屋上で待機。設置が完了したら、私とカオリでデータを入力する。基本的なプログラムはすでに組み上げてあるけれど、天候などによって多少のズレが出ることが予想される。その誤差は現場で調整するしかないからね」
「らいひょうふれふ! ひょはひがひょうひふひはひほも……」
カオリが、肉まんをほおばりながら立ち上がった。
ふざけているようだが、彼女が何か食べてるということは真剣ということだ。一所懸命になればなるほど、カオリは何かを食べてしまう。
ようやく肉まんを飲み込んだカオリが、改めて言い直した。
「大丈夫です! 初代が消失したときの時空曲線の洗い出しは完了しています。1ナノ秒の狂いもなくトレースしてみせます!!」
エドサキ博士がうなずいて、プリントをめくった。
残り3ページ。段階や担当ごとに区分してあるようだ。
「データ調整が終わったら、ミニたちのカプセルを起動する。今、彼らは、自らの維持システムさえも凍結して、本来の容量を大幅に上回る莫大なエネルギーを蓄えてくれているわ。それを一気に虚空の一点に集中させる。とてつもないエネルギーを、極小のピンポイントに撃ち込むの。そのために……」
「そこからが私の役目ね」
今度は、イバガールが口を挟んだ。
「カプセルの起動と完璧にシンクロして、私のエターナル・ウインド・フレアを発動させる。真空状態を作り出して、ミニちゃんたちのエネルギーを丸ごと全部、一切減衰させずに目標ポイントの空間まで届けてみせるわ!」
そこでガールは言葉を区切り、Rに向き直った。
「だからR……、その先は任せたわよ」
「わかってる。やってみせるさ、必ず!!」
イバガールの必殺技を利用して、大気中に素粒子実験と同じような加速トンネルを作り出すということだった。
強引すぎるやり方だから、完全な真空状態を維持できるのは一瞬だけだ。
全員がRを見つめた。
最後は、彼に託すしかない。
「そう、イバライガーRには最終段階を担ってもらうわ。全てのエネルギーを一点に集中させて、あのときと同じ特異点を開く。そこに飛び込んで、初代を見つけ出し、連れ戻す……」
教授の言葉を聞きながら、Rは拳を握り締める。
全員がそれに倣った。
その中で一人、ゴゼンヤマ博士だけが、首を振りながら座り込んだ。
「みんなには悪いが……私は……本当は中止してもらいたいよ」
「ゴゼンヤマ博士……?」
「ミニたちがどれほどのエネルギーを蓄えていても、本当に特異点を生み出せるかどうかは不確実だ。イバガールの風で真空を作るにしても、本来なら完全な真空を保った密閉空間で行うべきことだ。しかも、それらが全部成功したとしても、特異点が発生するほどの高エネルギー状態を維持できるのは、ほんの一瞬のはずだ……」
ゴゼンヤマ博士の声は暗い。
顔も、うつむいたままだった。
「私はみんなを止めたい。私も、初代が好きだ。様々な謎を解き明かすためにも、彼を取り戻したいとも思う。だが今回のことは……初代を連れ戻すどころか、Rまで失うかもしれない……」
他の誰も、声を発しなかった。
気持ちで盛り上がっていても、現実的に考えれば成功率はゼロに近い。賭けにもならない奇跡のようなことなのだ。
やらずにいられないからやる、というだけだ。
気持ちに区切りをつけるための儀式に過ぎないのかもしれない。
そんなことのためにRを危険にさらすのは、バカげたことだ。指摘されれば、その通りだった。
「……すみません、博士。私が初代と同じ力を使えさえすれば、より確実にやれたはずなのですが……」
「無理よ、R。今のあなたではね」
エドサキ博士が言った。
「確かにあなたと初代は、ほぼ同じ。外見だけでなく能力的にもね。だけど、あなたたちは初代に導かれて現代にやってきた。自分で時空を超えたわけじゃない。だから時空を突破するためのデータを持っていない。しかも未来の記憶を失っている。能力はあっても、使い方がわからない状態なのよ。あなたには、いえ、ガールやブラックも、時空突破の力は使えないはずよ」
Rがうつむいた。
シンは知っている。
Rが密かに、時空突破に挑戦し続けていたことを。
けれど、一度も成功していない。
というよりも、何をどうすればいいのかさえ分からない感じで、成功するとかしないというレベルにすら達していない。
「だから、みんなで力を合わせるんでしょ!!」
「でしょ!!」
ワカナとガールが、同時にツッコんだ。
「そのためにミニちゃんたちは力を溜めてるの。一瞬を少しでも長くするためにね。ナノ秒でもピコ秒でもいい。わずかでも特異点とのアクセス時間を延ばして成功率を高めて、Rと初代が一緒に帰ってこれるようにするために頑張ってるの」
「そうよ。全員の力を合わせて時空突破を成功させるの。大丈夫、きっとやれる。ていうか、いざとなったら私が、力ずくでも引き戻してみせるわよ!」
「ふっ」
笑いが漏れた。
ゴゼンヤマ博士が、顔を上げていた。
「キミたちは、やっぱりキミたちだなぁ。わずかな、可能性とも呼べないものに賭けて、何度でも立ち上がる。あきらめない。ヒーローってのは、全く困ったもんだ」
博士は立ち上がり、自分のパソコンを操作した。
何かのデータが、イバライガーRに転送されてくる。
「これは……?」
「初代イバライガーのデータだ。私がバックアップできた分だけだからカケラといった程度だが、それでもコレがキミを導いてくれるかもしれん」
「博士……」
「同意はできんが、だからといって私に止められるわけでもない。ならば、せめてキミの生還率を少しでも上げるだけだ」
博士が微笑んで、Rの肩を叩いた。
「う~ん、やっぱり博士もボクらの仲間だねぇ。ボケボケのジャークとも、今なら話できるんじゃないの?」
「い、いや、それはマーゴン、キミに任せる……」
「よっしゃあ! 必ず成功させるぞ~~~!!」
ワカナとガールがハイタッチしようとしたとき、エドサキ博士が割って入った。
「それはダメ!!」
言いながら、厳しい顔でRに向き直る。
「R、少しでも危ないと感じたら、すぐに引き返しなさい。失敗して当たり前。これはそういう作戦なの。失敗することが前提。成功させようなんて、決して思わないこと。そう思っていないと本当に帰ってこれなくなるわよ」
Rは、黙ってうなずいた。
途中でやめることができる性格ではないことは、全員が知っている。
それでも教授は、釘を刺さずにいられなかったのだろう。
「もぉ! 水を差さないでよぉ!」
ガールがプンスカしている。マーゴンが何かツッコんで、ガールが笑いだす。
緊張が解けて、雑談が始まった。
シンは黙ったまま、その光景を見つめていた。
ワカナも、ガールも、カオリも、マーゴンも、そしてRも、なんとか成功させようと思っている。
それはそれでいい。自分だってそのつもりだった。
だが、いざとなると、ゴゼンヤマ博士と同じ危惧がぬぐえない。
確かに何もせずにはいられない。戦略的にも、初代を取り戻せれば大きな力になるのは間違いない。
あえて無茶に挑むことで切り開ける未来があることも知っているつもりだ。
バタフライ・エフェクトというものがある。
風が吹けば桶屋が儲かる、北京で蝶が羽ばたくとニューヨークに台風が発生する。
カオス理論というヤツで、些細な出来事が連鎖的に重なって予測不能な何かにつながっていく。
歴史とは、予測できない些細で不条理な事象の積み重ねなのだ。
何が歴史の転換点なのかは、誰にもわかりはしない。
イバライガーたちがいた未来がどうであったとしても、今は違う。全く別の『オレたちの歴史』なのだ。
結果が確定するまでは、あらゆる可能性が入り交じった混沌なのだ。
だからオレたちは、今やれることをやるしかない。
しかし本当に、これでいいのか。
もっと確実性を上げる方法があるのではないのか。
オレたちは感情的になりすぎていないか。焦って軽率な決断をしていないか。
不慣れどころか全く未経験のRに、自分たちの身勝手な気持ちを押し付けてしまったのではないのか。
ここまで来たら、やるしかない。
やるからには、迷いは捨てるべきだ。
だが……。
「うわぁあああああああああああああっ!!」
突然、カオリが叫んだ。同時にRとガールが、弾かれたように飛び出していく。
カオリは、モニターの1つを指差して震えている。
周辺の監視カメラのモニターだった。
ジャークならば、イバライガーたちのセンサーが見逃しはしない。
遠く離れてしまうと、普通の人々のネガティブ感情に紛れてしまって探知できないが、数キロ圏内に近付けば、ジャーク反応は確実に捉えられるはずだ。
監視カメラは、人間たちを警戒してのものだった。
例えばTDF。彼らがここに気付いていることは確実で、いつイバライガーを接収しようと踏み込んでくるか分からない。
また、この隠れ家は街のど真ん中にある。往来の多い場所だから、誰かが迷い込んでくる可能性もある。
出入り口は偽装してあるが、それでも万全とまでは言えない。だから周囲には、いくつもの監視カメラを設置してあるのだ。
その1つ、大通りをモニターしているカメラ。
いつも通りの風景が映っている。
「い、い、い、今プレイバックします!!」
30秒ほど前のシーンが再生される。
タクシーが止まった。女が降りる。ヘンな動きの女だ。
あ、あれ? ドアを開けたまま走り出したぞ。うわ、他の車にぶつかってるよ。そのまま走っていっちゃった。
降りた女が、顔を上げた。
カメラの存在に気付いているように、こちらを見て嗤った。
ナツミ!?
いや、ルメージョ!?
「ジャークがタクシーでやってきた!?」
「そんなバカな!?」
「馬鹿が戦車でやってくるほうが、まだ信じられるよ!」
「いや、それもないって!!」
「ちょっと黙って!!」
ワカナが怒鳴って、モニターのコントロールパネルに飛びついた。
スロー再生する。
女が降りる。ギクシャクした気味の悪い動き。
立ち止まり、タクシーのほうを振り返ろうとする。ギギギ……と、きしむ音が聞こえそうな動きだ。
その一瞬、横顔が見える。ワカナは画面を止めた。
「これは……この顔は……!」
シンが肩を叩いた。
「オレも気付いた。たぶん、あれはナッちゃんだ。夢遊病者みたいな、うつろな表情だけど、ルメージョじゃない。そうか、そういうことか……」
言いながら、コンパネのスライダーを動かす。
女の顔が、もう一度こちらに向き直って、カメラを見る。
今度はルメージョだ。同じ顔だが、違う。ナツミだったのは、横顔の一瞬だけだ。
「そういうことって、どういうこと?」
「ルメージョは自分を身体の奥に沈めてナツミに渡し、体外に漏れない程度のわずかな気で内側から操っていたんだろう。恐らくは、Rたちのセンサーを欺くために」
人間になりきれるジャーク。
ワカナはゾッとした。
ナツミを残しているのは、その知識や私たちとの関係を利用するためだろうと思っていたけど、そんな使い方があったなんて。
モニターを、リアルタイム映像に戻した。
ビルの正面を捉えているモニターが、ナツミ=ルメージョを映し出した。
Rとガールはいない。
おかしい。
ルメージョに戻った瞬間の反応をキャッチしたからこそ、二人は飛び出していったはずだ。
敵は目の前。とっくに対峙しているはず。
インカムを掴んだ。
「R、ガール。どこにいるの!?」
「……屋上だ」
スピーカーからのRの声が、室内に響いた。
「R! ルメージョが……!!」
ワカナからインカムを引ったくったシンが怒鳴った。
「わかっている。だが、今はそれどころじゃない」
「何なの、アレ!?」
ガールの声だ。
「R、ガール、映像を送ってくれ。4番のモニタでいい」
画面が切り替わった。空。
全員が、息を飲んだ。
黒い球体が浮かんでいる。大きい。直径20メートル以上はありそうだ。
しかも少しずつ膨張しているようにも見える。
「こ、これは……!?」
※このブログで公開している『小説版イバライガー』シリーズは電子書籍でも販売しています。スマホでもタブレットでも、ブログ版よりずっと読みやすいですので、ご興味がありましたら是非お読みいただけたら嬉しいです(笑)。








 うるの拓也
うるの拓也












